COLUMN
コラム
SCROLL
2025.08.04 税務コラム
法人の青色申告の条件とメリットを解説/税務コラム~[vol.018]
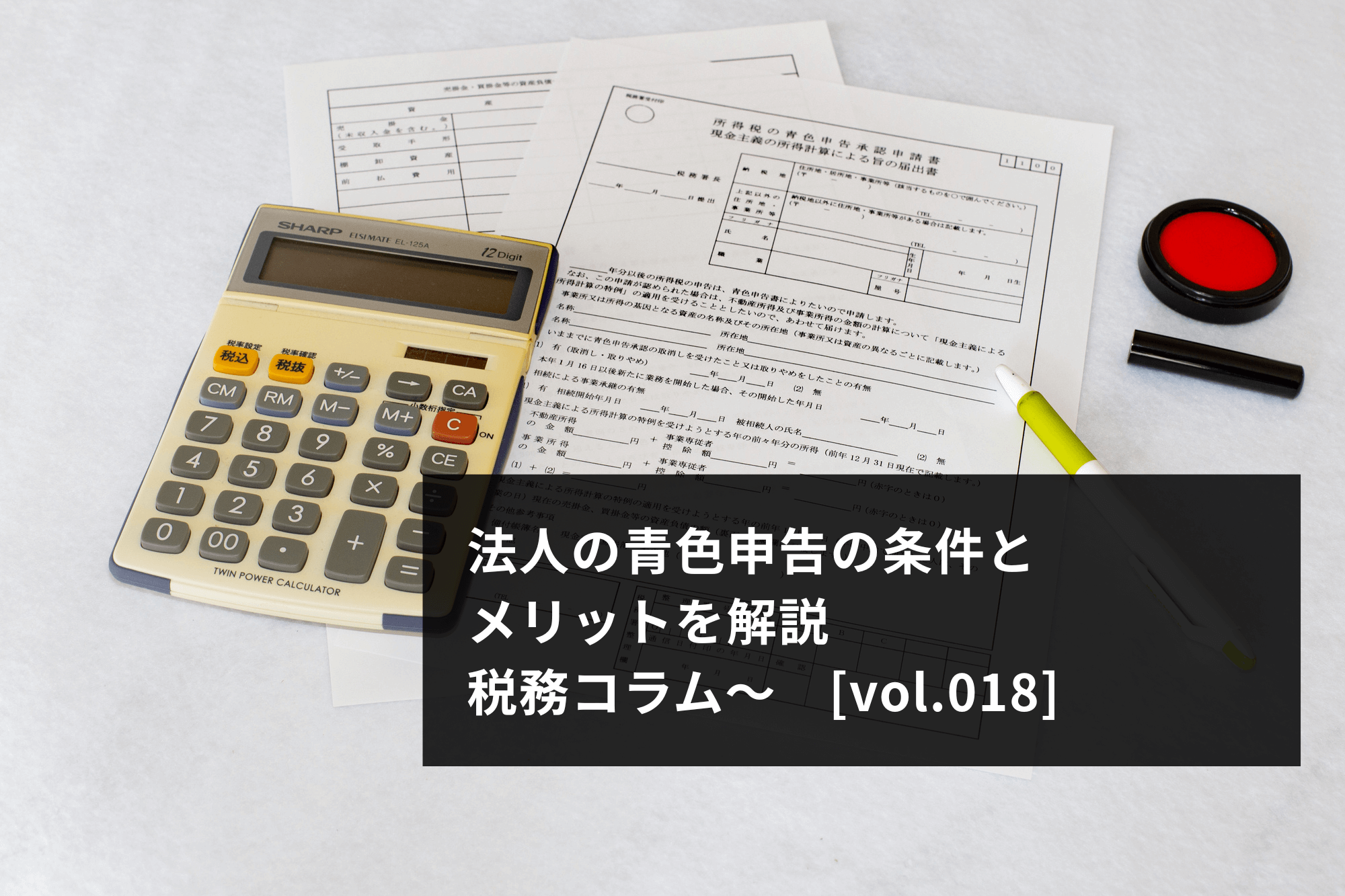
日本の法人の99%が青色申告を選んでいることをご存知でしょうか?かつては白色申告との違いも大きかったですが、現在では記帳の必要性など、両者の違いはほとんどなくなっています。では、なぜこれほど多くの法人が青色申告を選択するのでしょうか。
この記事では、法人が青色申告を利用するための条件から、青色申告がもたらすメリットを解説します。青色申告を検討している経営者の方、すでに青色申告をしているがメリットを活用できていないと感じている方は、ぜひ参考にしてください。
日本の法人の99%が青色申告
国税庁の令和5年度分の標本調査結果によると、単体法人で青色は2,912,274社、白色は26,888社となっており、青色申告の法人の割合は99%に及びます。
最近は99%で推移していますが、平成に入るまではそれほど高くありませんでした。その理由としては白色申告に記帳が必要なかったことが挙げられますが、今では白色申告でも記帳が必要となり、両者の間にそれほど違いがなくなりました。なお、個人事業主では青色申告の割合は60%弱となっています。
法人の青色申告の条件
青色申告の承認申請書の提出
青色申告の承認申請書を必ず提出する必要があります。
期限は、青色申告をしようとする事業年度が始まる前までになります。申請書になりますが、青色申告をしようとする事業年度末までに却下の通知がない場合には、承認があったものとみなされます。みなし承認と呼ばれます。
設立1期目から青色申告をする場合には、設立した日から2か月以内に提出する必要があります。設立登記を済ませて、定款や登記簿謄本を揃えてから、設立届出と一緒に提出することが多いと思いますが、時間があるようでありませんので、忘れずに提出するようにしましょう。
帳簿書類の備付け、記録又は保存
帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、帳簿書類を保存しておく必要があります。
帳簿については、一般的に複式簿記により主要簿である仕訳帳や総勘定元帳を作成することになります。青色申告の承認申請書の提出時において、税務署が仕訳帳や総勘定元帳が作成されているかどうかを確認することはしませんが、後の税務調査の際には、総勘定元帳を当然のように確認します。
領収書、請求書、契約書などの証拠書類も、帳簿と紐付けて整理し、保存することが求められます。
これらも税務調査の際に、記載内容の根拠として提示を求められます。
令和4年1月1日以降、電子帳簿保存法が改正され、電子的にやり取りした取引情報(電子データ)は、原則として電子データのまま保存することが義務付けられましたので注意が必要です。
帳簿書類の保存期間は7年間ですが、青色繰越欠損金が生じた事業年度では10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)になります。
法人の青色申告のメリット
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告最大のメリットは欠損金の繰越です。青色申告の事業年度において欠損金が生じた場合には、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)繰り越して、所得が発生したときに控除することができます。かつては5年間でしたが、7年、9年、10年と徐々に長くなっています。
資本金1億円以下の法人などの中小企業者等には青色欠損金の繰戻もあります。青色欠損金の控除とは逆となり、前期が納税で今期は欠損の場合には、欠損金額の法人税率相当額(以下の計算式で計算した金額)の還付を受けることができます。
前期の法人税額×今期の欠損金額/前期の所得金額
要件として、今期の申告の際に繰戻還付請求書を申告書と一緒に提出する必要があります。
中小企業等の少額減価償却資産の損金算入
中小企業者等は30万円未満の減価償却資産の取得価額を一時の経費にすることができます。少額減価償却資産と呼ばれます。年間で合計300万円までになります。
10万円未満は青色申告に関係なく、一時の経費として計上することができますが、更に増えて30万円までになります。例えば、パソコンなどは10万円を超えるので利用することができます。
ただし、少額減価償却資産として法人税では一時の経費にすることができますが、地方税の償却資産(固定資産税)申告では対象に含めることになります。償却後の評価額(課税標準額)が免税の基準である150万円を超えてきますと固定資産税が発生してきます。そういった場合には、10万円から20万円の減価償却資産については、法人税では一括償却資産として3年にわたって経費に計上することを検討します。一括償却資産ですと地方税の償却資産(固定資産税)申告の対象にはなりません。
貸倒引当金の特例
中小企業者等は事業年度末における売掛金や受取手形などの債権に対し、業種ごとの一定の割合で貸倒引当金を繰り入れることができます。将来の貸倒れに備えてあらかじめ費用を計上することができます。
| 業種区分 | 法廷繰入率 |
|---|---|
| 卸売業・小売業(飲食店業及び料理店業を含む) | 10/1000 (1.0%) |
| 製造業(電気業・ガス業・水道業・ 熱供給業・修理業を含む) | 8/1000 (0.8%) |
| 割賦販売小売業・割賦購入あっせん業 | 7/1000 (0.7%) |
| 金融業・保険業 | 3/1000 (0.3%) |
| 上記以外の業種 | 6/1000 (0.6%) |
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
中小企業者等が設備に投資した場合には、特別償却または特別控除の選択適用が可能です。特別償却は、取得価額の30%を追加で償却します。特別控除は、取得価額の7%を法人税額から控除します(法人税額の20%が限度)。中小企業投資促進税制と呼ばれます。
対象は新品の設備で、以下のような金額基準等が設けられています。
| 設備の種類 | 要件 |
|---|---|
| 機会及び装置 | 1台または1基の取得価額が160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 1台または1基の取得価額が120万円以上 1台30万円以上かつ複数合計で120万円以上 |
| ソフトウェア | 一の取得価額が70万円以上 |
| 器具備品 | 1台または1基の取得価額が30万円以上 (一部の例外あり) |
| 建物附属設備 | 一の取得価額が60万円以上 |
| 普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
| 内航船舶 | 取得価額の75%が対象 |

監修者プロフィール
川口 誠(カワグチ マコト)
国税局では高度な調査力が必要とされる調査部において、10年以上にわたって上場企業や外国法人等の税務調査に従事する。また、国税庁においては、全国の国税局にある調査部の監理・監督を行い、国税組織の事務運営にも携わる。
略歴
平成24~28年 東京国税局 調査第四部各調査部門、調査第一部調査管理課
平成29~30年 国税庁 調査査察部 調査課
令和元~5年 東京国税局 調査第一部 国際調査課、国際調査管理課、広域情報管理課
令和6年 ON税理士法人と業務提携
実績
中小企業から上場企業等まで100以上の会社の税務調査を行う。
メディア・著書
「元国税の不動産専門税理士が教える!不動産投資 節税の教科書」
資格・免許
税理士
CONTACT各種お問い合わせ
税務に関するあらゆる課題は
ON税理士法人に
お任せください
お電話でのお問い合わせ






