COLUMN
コラム
SCROLL
2025.09.25 税務コラム
個人事業主の家族給与は経費になる?―青色事業専従者給与と事業専従者控除の活用―/税務コラム~[vol.020]
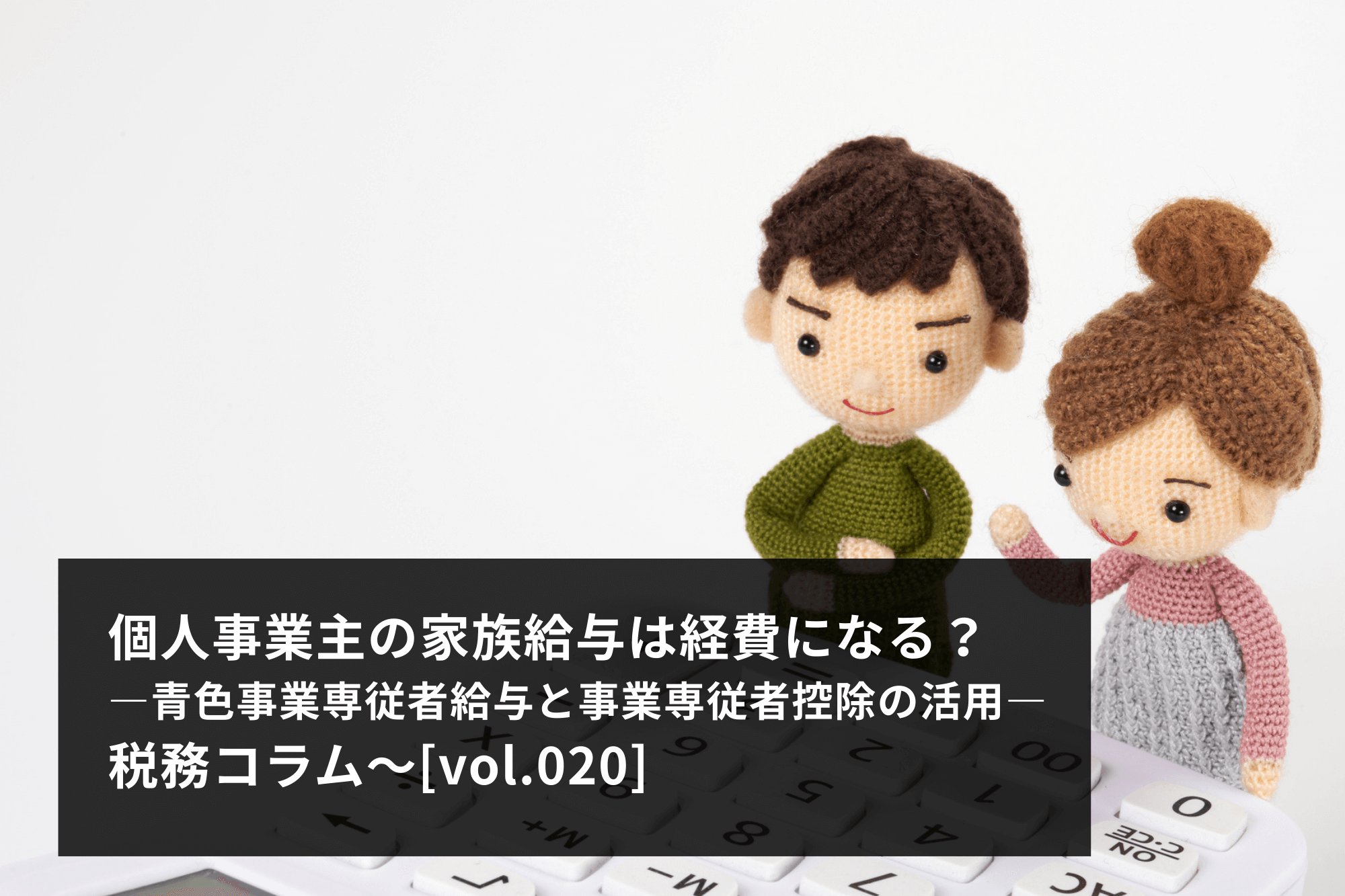
個人事業主として事業を営む中で、配偶者や親族に手伝ってもらう機会は多いと思います。こうした家族に支払う給与は、経費にできるのかと疑問に思ったことはありませんか?特定の要件を満たすことで、家族への給与を経費として計上し、節税効果を得ることができます。
この記事では、個人事業主が家族に給与を支払うことができる制度「青色事業専従者給与」と「事業専従者控除」について、それぞれの要件や注意点を解説します。
CONTENTS
個人事業主が給与を払える場合
個人事業主自身には「給料」という概念がありません。事業の売上から経費を差し引いた残りが、そのまま事業主の所得となります。そのため、事業主が自分の生活費として事業用のお金を引き出す場合は、会計上「事業主貸」という勘定科目を使って処理します。これは、あくまで事業主個人の資金移動であり、経費にはなりません。もし自分自身への給料を経費として計上したい場合には、法人化を検討する必要があります。法人では、社長(役員)への報酬は「役員報酬」として経費にできます。
個人事業主が家族以外の従業員を雇い、給料を支払う場合は、その給料は事業の経費として全額計上できます。個人事業主が生計を共にする家族(配偶者や親族)に給料を支払う場合、原則として経費にすることはできません。しかし、「青色事業専従者給与」「事業専従者控除」といった制度を利用することで経費にできる場合があります。
なお、給与を支払う事務所を開設した日から1ヶ月以内に、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する必要があります。従業員に支払う給料から所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付する義務が生じます。また、健康保険や厚生年金保険への加入手続きが必要になってくることもあります。
青色事業専従者給与の要件
青色事業専従者給与を必要経費として計上するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
青色申告者であること
この制度は青色申告者のみが利用できます。白色申告者が家族に給与を支払う場合は「事業専従者控除」という別の制度を利用することになります。
青色事業専従者であること
控除の対象となる家族は、以下のすべての条件を満たす「青色事業専従者」でなければなりません。
- ・生計を一つにする配偶者や親族であることです。これは、同じ家計で生活している家族を指します。たとえ別居していても、生活費を送金しているような場合は「生計を一つにする」とみなされます。
- ・その年の12月31日時点で、給与を支払う家族が15歳以上であることが条件です。
- ・事業に「専ら」従事していることです。これが最も重要な要件です。その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していなければなりません。「専ら」とは、その事業にほぼ専念している状態を指します。他で正社員として働いていたり、学業が本分である学生(高校生や大学生など)であったりする場合は、原則として認められません。週末だけ手伝う、といったような関わり方では「専従」とは認められません。ただし、事業に従事できる期間の半分以上をその事業に費やしている場合など、一定の例外はあり、個別に判断する必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに、所轄の税務署にこの届出書を提出する必要があります。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内です。
この届出書には、給与を支払う家族の氏名、仕事内容、給与の金額などを具体的に記載します。
この届出書に記載した金額の範囲内でしか、給与を経費にすることはできません。
給与額が「妥当」であること
給与額を決める際は、仕事内容、労働時間、同業種の給与水準などを客観的に見て妥当な金額に設定することが最も重要です。それに加えて、家族全体の所得税や社会保険料の負担を考慮して調整することで、より効果的な節税につながります。
もし給与額が明らかに高すぎる場合は、その超過分は経費として認められません。
青色事業専従者給与の金額設定
青色事業専従者給与の「妥当な金額」は、一概に「いくら」と決まっているわけではありません。税務上は、以下の要素を総合的に判断して決定します。
- ・仕事の内容
- ・労働時間
- ・事業の規模や種類
- ・同種の事業に従事する他の従業員への給与水準
これらの要素を客観的に見て、「労務の対価として相当と認められる金額」であることが求められます。
以下は、金額を考える上で参考となる情報になります。
年間103万円以下
専従者が所得税の基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額の範囲内となり、専従者自身の所得税が非課税になります。家族全体の税負担を最適化する上で、よく考慮される金額です。
月額8.8万円未満
源泉徴収義務が発生しない金額です。年間約105万円(8.8万円 × 12ヶ月)の給与になります。専従者側の所得税や住民税の負担も少なく、事業主側の経理処理も簡素化できるため、この金額を目安にしている方もいます。
月額8.8万円未満であっても、扶養控除等申告書を提出していない場合には源泉徴収が必要となるケースがあります。
同業種の平均給与
「妥当」を判断する上で、一番重要な判断基準となります。
国税庁の統計(標本調査結果)によると、青色事業専従者1人当たりの平均給与額は約210〜220万円とされています。ただし、これはあくまで全体の平均であり、個々の事業の状況によって大きく異なります。
自分の事業と同じ業種で、似たような業務(事務、営業、技術など)をしている従業員が、どのくらいの給与をもらっているかを参考にします。例えば、事務作業を任せているのであれば、一般的な事務職のパートやアルバイトの時給を参考に、年間勤務時間から給与額を算出します。
事業主自身の所得とのバランス
専従者給与を支払うことで、事業主の所得が極端に少なくなる場合は、給与額が過大と見なされる可能性があります。例えば、事業主の所得が600万円であるにもかかわらず、専従者に300万円の給与を支払うと、バランスが悪いと判断される可能性があります。
実際の金額設定のポイント
- ・届出書に記載した金額は、あくまで支給可能な上限額です。実際の支給額がこの金額を下回っても問題ありません。
- ・事業主の所得税率と、専従者の所得税率を比較し、家族全体での税負担が最も軽くなるような金額を設定することが理想です。
- ・税務調査が入った際に、その金額が妥当であることを説明できるよう、同業種の求人情報や賃金統計などの資料を準備しておくと安心です。
最終的には、事業の状況や専従者の実際の働きぶりを考慮し、客観的に見て「妥当」と判断できる金額を設定することが最も重要です。迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
事業専従者控除の要件
事業専従者控除は、白色申告の個人事業主が家族従業員に対する給与を経費としてではなく、一定の金額を所得から控除できる制度です。
この控除を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
白色申告者であること
この制度は白色申告者のみが利用できます。青色申告者は「青色事業専従者給与」の制度を利用するため、この控除は適用できません。
事業専従者であること
控除の対象となる家族は、以下のすべての条件を満たす「事業専従者」でなければなりません。
- ・白色申告者と生計を一つにする配偶者や親族で、同じ家計で生活していることです。
- ・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であることが条件です。
- ・その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に「専ら」従事していること。「専ら」とは、その事業にほぼ専念していることを意味します。
確定申告書に記載すること
「事業専従者控除」を受けるためには、確定申告書の第二表に「事業専従者に関する事項」を記載する必要があります。青色申告のような事前の届出は必要ありませんが、確定申告時に控除を受ける旨を記載することが要件です。
事業専従者控除の金額
事業専従者控除の金額は、以下のいずれか低い方の金額になります。
- ・法定控除額
事業専従者が事業主の配偶者である場合:86万円
事業専従者が事業主の配偶者以外の親族である場合:1人につき50万円
- ・(控除前の事業所得等の金額)÷(専従者の数+1)
この2つの金額を比較して、低い方が控除額となります。
例えば、事業所得が300万円、事業専従者は配偶者1人ですと、計算式による控除額は150万円(=300万円 ÷ (1人 + 1) )となりますが、 法定控除額86万円の方が低いので、86万円が事業専従者控除額となります。
青色事業専従者給与と事業専従者控除の注意点
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、事業主の配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。どちらか一方しか受けられないため、どちらが節税になるか比較検討する必要があります。
青色事業専従者給与と異なり、事業専従者控除は実際に給与を支払ったかどうかは要件とされていません。たとえ家族に給与を支払っていなくても、上記の要件を満たしていれば控除を受けることができます。事業専従者控除は、実際の給与額にかかわらず定額です。そのため、支払った給与が控除額より多い場合でも、超過分は経費にできません。
これらの要件と注意点を理解し、青色事業専従者給与と事業専従者控除の適用を検討することが大切です。

監修者プロフィール
川口 誠(カワグチ マコト)
国税局では高度な調査力が必要とされる調査部において、10年以上にわたって上場企業や外国法人等の税務調査に従事する。また、国税庁においては、全国の国税局にある調査部の監理・監督を行い、国税組織の事務運営にも携わる。
略歴
平成24~28年 東京国税局 調査第四部各調査部門、調査第一部調査管理課
平成29~30年 国税庁 調査査察部 調査課
令和元~5年 東京国税局 調査第一部 国際調査課、国際調査管理課、広域情報管理課
令和6年 ON税理士法人と業務提携
実績
中小企業から上場企業等まで100以上の会社の税務調査を行う。
メディア・著書
「元国税の不動産専門税理士が教える!不動産投資 節税の教科書」
資格・免許
税理士
記事に関連する当事業内容
記事に関連する
当事業内容
CONTACT各種お問い合わせ
税務に関するあらゆる課題は
ON税理士法人に
お任せください
お電話でのお問い合わせ



