COLUMN
コラム
SCROLL
2025.10.14 税務コラム
個人事業主ができる節税対策10選/税務コラム~[vol.022]
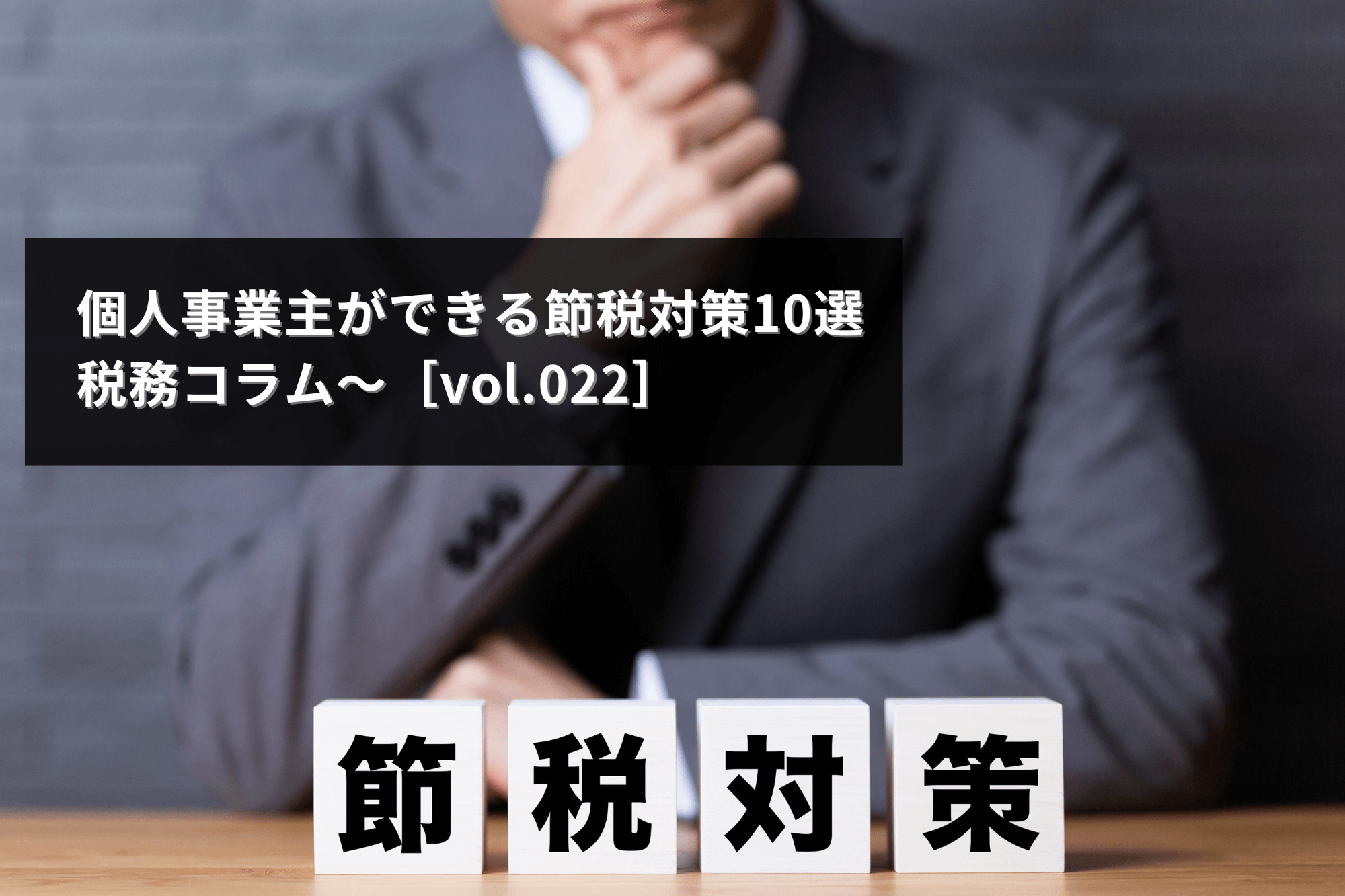
個人事業主が知っておくべき基本的な節税の考え方から、いますぐ始められる具体的な方法、
さらには将来を見据えた節税対策まで幅広くご紹介します。
節税の基本:経費を漏れなく計上する
節税の第一歩は、経費をきちんと把握し、漏れなく計上することです。所得税は売上から経費を引いた後の所得に対して課税されます。つまり、経費が多ければ多いほど、所得が減り、税金も安くなるのです。
経費とは、事業を行う上で必要な費用を指します。以下に代表的な経費の例を挙げます。
| 勘定科目 | 例 |
|---|---|
| 消耗品費 | 文房具、プリンターのインク、USBメモリなど |
| 通信費 | インターネット回線料金、携帯電話料金、 電話代など |
| 旅費交通費 | 出張にかかる電車代、バス代、タクシー代、 宿泊費など |
| 広告宣伝費 | ホームページ制作費、広告掲載料、名刺作成費など |
| 外注費 | 業務委託料など |
| 水道光熱費 | 事業で使用した電気代、水道代、ガス代 |
| 家賃 | 事業所として使用しているオフィスの家賃 |
自宅の一部を事務所として使っている場合、家賃や水道光熱費、通信費などを経費にできます。
ただし、事業に使っている部分とプライベートな部分を区別し、合理的な割合で按分する必要があります。例えば、部屋の面積や使用時間で按分するのが一般的です。
経費を証明するためには、領収書やレシートの保管が大切になってきます。最近では、スマホアプリでレシートを撮影してデータ化するサービスも多く、管理が楽になっています。
青色申告のメリットを最大限に活用する
個人事業主の税務申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。節税を考えるのであれば、断然青色申告がおすすめです。青色申告には、白色申告にはない様々な特典があります。
青色申告を行うためには、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
65万円の青色申告特別控除
青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除です。複式簿記による記帳と帳簿保存を行い、
かつ、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除が適用されます。所得が65万円減ることで、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の負担も軽減されます。
青色事業専従者給与
15歳以上の家族で、6か月超にわたり専ら事業に従事していることなどの要件を満たせば、給与を必要経費にできます。これを青色事業専従者給与といいます。ただし、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出」を提出する必要があります。
欠損金(赤字)の繰り越し
事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。例えば、初年度が赤字でも、翌年黒字になった際に前年の赤字を相殺し、納税額を減らすことができます。これは白色申告にはない制度です。
所得控除を漏れなく利用する
所得控除は、所得から差し引くことができる項目です。所得が減ることで、税金の負担が軽くなります。代表的な所得控除には以下のようなものがあります。これらの控除を受けるためには、確定申告の際に控除に係る書類を用意して、金額を把握する必要があります。
| 所得控除 | 内容 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民年金保険料、国民健康保険料など、自分で支払った社会保険料の全額が控除対象です。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険や個人年金保険の保険料の一部が 控除対象です。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険の保険料が控除対象です。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCoの掛金が 全額控除対象となります(後述)。 |
| 医療費控除 | 1年間の医療費が一定額を超えた場合、 超過分が控除対象です。 |
| 扶養控除 | 扶養している家族がいる場合に控除が 受けられます。 |
退職金制度を活用する節税対策
ここからは、将来の資産形成と節税を両立できる、個人事業主向けの節税対策をご紹介します。これらは支払った掛金が全額所得控除になるのが最大の魅力です。所得が減ることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
小規模企業共済
小規模企業共済は、「経営者のための退職金制度」と呼ばれる国の制度です。個人事業主や小規模企業の経営者が加入でき、積み立てた掛金は将来、退職金や解散金として受け取れます。
毎月1,000円から70,000円までの範囲で自由に掛金を設定でき、その全額が所得から控除されます。
年間で最大84万円も控除できるため、大きな節税効果が期待できます。共済金(退職金)として受け取る際も、年金として受け取る際は公的年金等控除、一時金として受け取る際は退職所得控除の対象となり、税制上の優遇があります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で掛金を積み立てて運用し、将来年金として受け取る制度です。個人事業主にとって、老後の資金準備と節税を同時に進められる非常に有効な手段です。
支払った掛金は全額所得控除の対象となります。運用で得られた利益には税金がかかりません。通常、投資で得た利益には20.315%の税金がかかるので、これは非常に大きなメリットです。退職所得控除や公的年金等控除の対象となり、税金が軽減されます。
iDeCoは、元本保証型の商品から投資信託まで、様々な運用商品の中から自分で選択できます。将来の資産形成を積極的に行いたい方におすすめです。
その他の節税対策
ふるさと納税
ふるさと納税は、自分の故郷や応援したい自治体に寄附をすることで、寄附金控除が受けられる制度です。寄附した金額のうち2,000円を超える部分は、所得税や住民税から控除されます。また、寄附のお礼として、その地域の特産品などを受け取れることも大きな魅力です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備えるための共済制度です。個人事業主も加入でき、万が一取引先が倒産した場合、積み立てた掛金の10倍の範囲内で融資を受けることができます。
支払った掛金は全額経費にできます。年間最大240万円まで経費にできるため、高い節税効果があります。
12ヶ月以上掛金を支払って解約した場合、掛金の総額に応じて解約手当金が受け取れます。40ヶ月以上で全額が戻ってきます。
解約手当金を受け取った際は事業所得の収入として計上する必要があります。掛金を支払った年に経費として処理し所得を圧縮していた分、解約手当金を受け取った年はその分だけ所得が増えることになります。そのため、解約のタイミングを検討する際は、その年の所得状況や税負担のバランスを考慮する必要があります。
経営者年金保険
経営者年金保険は、個人事業主が自身の老後の生活資金を準備するための年金保険です。一定額までなら、支払った保険料が生命保険料控除の対象となります。
加入する保険の種類(養老保険、終身保険、個人年金保険など)によっては、保障と同時に貯蓄性を持っています。年間支払額のうち、一定額が所得控除の対象となります。所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除が受けられます。
節税は知識の有無で結果に大きな差が出る分野です。この記事で紹介した【経費計上、青色申告、iDeCo・小規模企業共済】の3つの柱を実践することによって税負担は軽減される可能性があります。まずは青色申告の申請や経費の整理など、「いますぐできること」から行動に移してみましょう。複雑な手続きや判断に迷ったら、一度税理士に相談してみてください。

監修者プロフィール
川口 誠(カワグチ マコト)
国税局では高度な調査力が必要とされる調査部において、10年以上にわたって上場企業や外国法人等の税務調査に従事する。また、国税庁においては、全国の国税局にある調査部の監理・監督を行い、国税組織の事務運営にも携わる。
略歴
平成24~28年 東京国税局 調査第四部各調査部門、調査第一部調査管理課
平成29~30年 国税庁 調査査察部 調査課
令和元~5年 東京国税局 調査第一部 国際調査課、国際調査管理課、広域情報管理課
令和6年 ON税理士法人と業務提携
実績
中小企業から上場企業等まで100以上の会社の税務調査を行う。
メディア・著書
「元国税の不動産専門税理士が教える!不動産投資 節税の教科書」
資格・免許
税理士
記事に関連する当事業内容
記事に関連する
当事業内容
CONTACT各種お問い合わせ
税務に関するあらゆる課題は
ON税理士法人に
お任せください
お電話でのお問い合わせ



