COLUMN
コラム
SCROLL
2025.10.27 税務コラム
「修正申告」と「更正の請求」の違いと実務対応【税務調査との関係も解説】/税務コラム~[vol.023]
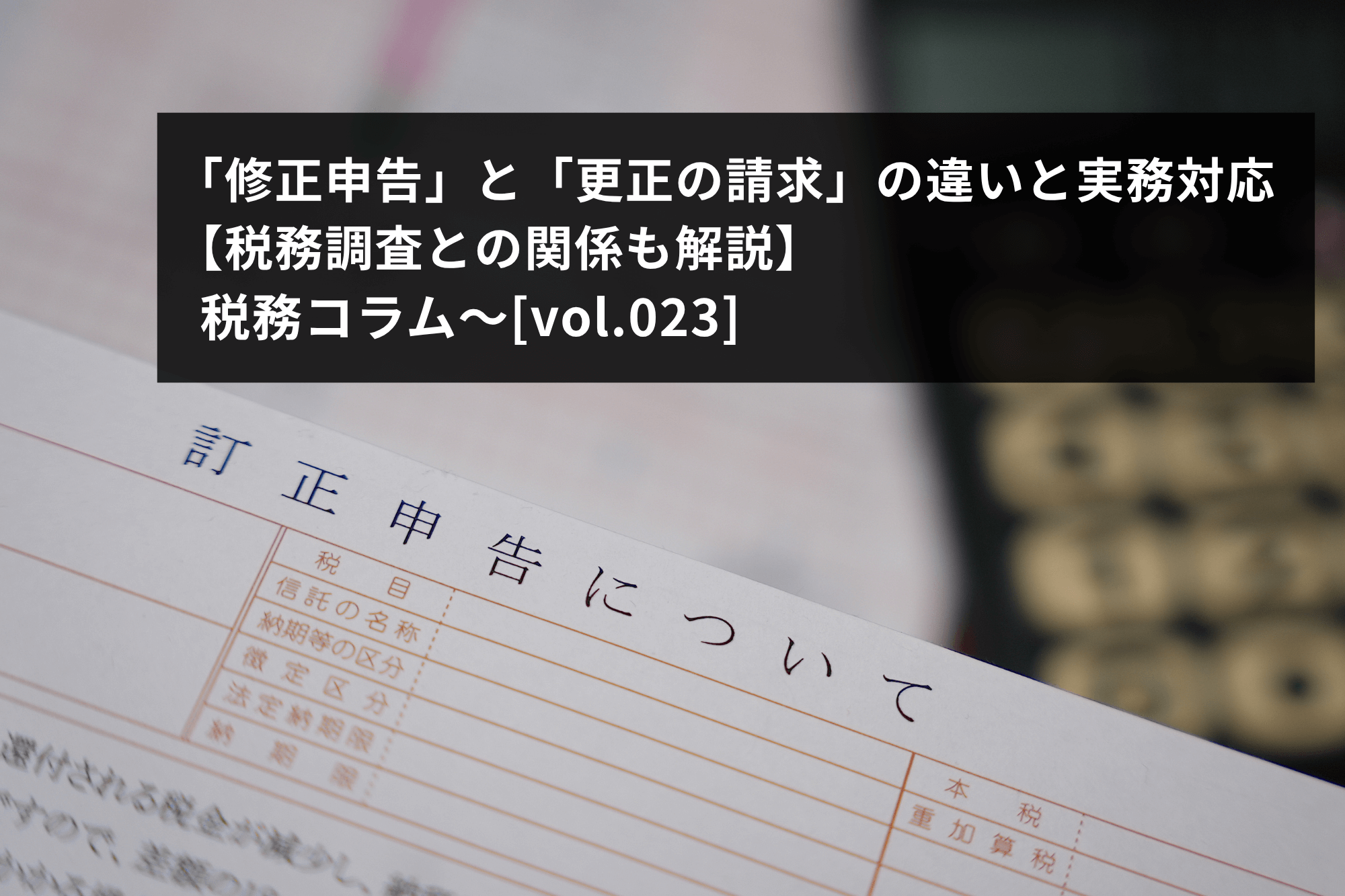
確定申告を終えたあと、「申告内容に誤りがあった」と気づくことがあると思います。このときに取り得る手続きが「修正申告」と「更正の請求」です。いずれも「確定申告後に税額を訂正する」制度ですが、目的・性質・効果はまったく異なります。
ここでは、両者の違いと実務上の注意点、そして税務調査との関係までを整理して解説します。
CONTENTS
修正申告の基本 ― 納める税額が少なかった場合
制度の概要
修正申告とは、確定申告に誤りがあり、本来納めるべき税額が少なかった場合に、納税者自ら正しい税額を再計算して申告する手続きです。例えば、申告漏れの所得があったり、控除を誤って多く計上していたりする場合などが該当します。
目的と法的性質
修正申告の目的は、不足していた税金を自主的に納付し、正しい納税義務を果たすことです。これはあくまで納税者の意思による申告行為であり、提出と同時にその税額が確定します。税務署の許可や判断を待つものではありません。
結果と附帯税(加算税・延滞税)
修正申告を行うと、追加の本税に加えて、過少申告加算税(税務調査では追加本税の10%)と延滞税(法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて)が課されることがあります。
ただし、後述のように「自主的に修正した場合」は、過少申告加算税が軽減されます。
更正の請求の基本 ― 納める税額が多すぎた場合
制度の概要
更正の請求とは、確定申告で税額を多く納めすぎた、あるいは還付金を少なく申告していた場合に、納税者が税務署に対して「減額してほしい」と求める手続きです。例えば、医療費控除を申告し忘れていた、経費を計上し忘れていた、二重課税が発生していた、などのケースがあります。
目的と法的性質
更正の請求の目的は、払い過ぎた税金の返還を求めることです。
ただし、修正申告と違い、納税者の請求だけでは税額は確定せず、税務署が内容を審査して認めた場合に初めて減額更正が行われます。このため、納税者の請求が認められないこともあります。
期限と手続き
更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行うのが原則です(例:所得税であれば、原則として申告をした年の翌年3月15日から5年以内)。請求書には、訂正の理由・根拠資料・正しい税額の計算を明示し、証拠となる書類を添付する必要があります。税務署が請求を認めれば、「更正通知書」が送付され、還付金が振り込まれます。
逆に、認められなかった場合は「更正すべき理由がない旨の通知書」が送られ、不服があれば再調査請求・審査請求などの「不服申立て」の手続きに進むことができます。税務署から「更正すべき理由がない旨の通知書」が届いた場合、納税者はその通知があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、税務署長に再調査請求、または国税不服審判所長に審査請求を行うことができます。この手続きは、税務署の判断を覆すための重要な権利であり、納得がいかない場合は専門家(税理士や弁護士)と相談の上、速やかに対応を検討する必要があります。
修正申告と更正の請求の比較表
| 項目 | 修正申告 | 更正の請求 | ||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 税額が少なすぎた (還付が多すぎた) | 税額が多すぎた (還付が少なすぎた) | ||
| 手続きの性質 | 納税者による申告 (自主修正) | 納税者による請求 (税務署に判断を求める) | ||
| 税額の確定 | 申告により確定 | 税務署の判断により確定 | ||
| 結果 | 追加納税+加算税+延滞税の可能性 | 還付(税務署が認めた場合) | ||
| 不服申立て | 不可 | 却下された場合に可能 | ||
修正申告の実務と注意点
提出のタイミング
修正申告は、税務署による「更正」前であればいつでも可能です。特に、税務調査の前に誤りに気づいた場合には、早めに自主的な修正申告を行うことで加算税の軽減を受けられます。
加算税の軽減措置
修正申告のタイミングによっては過少申告加算税が軽減されます。
- ・税務調査の調査通知前に自主的に修正申告した場合 → 加算税なし
- ・調査通知後・実地調査前に修正申告した場合 → 加算税5%
- ・調査後・指摘を受けて修正した場合 → 原則10%
(隠ぺい・仮装など悪質な場合は重加算税35%または40%)
このように、自主的な是正はペナルティ軽減の最も有効な手段です。
更正の請求の実務と留意点
提出の流れ
更正の請求書を税務署に提出すると、税務署は内容の正当性を確認します。請求内容が明確で証拠が揃っていればスムーズに処理されますが、曖昧な場合は調査が行われることもあります
期限延長(後発的事由)
法定期限(5年)を過ぎても請求できる場合があります。例えば、裁判の判決により課税根拠が消滅した、他の所得区分の訂正に伴う影響が生じた、など「後発的な事由」があるときは期限が延長されます(国税通則法第23条第2項)。
税務調査と修正申告の関係
税務調査の現場では、修正申告がしばしば登場します。調査で誤りが見つかった場合、納税者は次の2つの選択肢を取ることになります。
修正申告書を提出する場合
調査官の指摘を受け入れて自ら修正申告を行うと、調査は比較的円滑に終了します。また、調査開始前に自主的に修正していれば過少申告加算税が軽減されるため、結果的に有利になることが多いです。
ただし、修正申告書を提出すると、それは納税者自身の意思による申告となるため、その後に再調査請求・審査請求などの「不服申立て」はできません。
修正を拒否して「更正」を待つ場合
もし指摘内容に納得できない場合は、修正申告を行わず、税務署長による「更正」を待つことができます。この場合、更正処分に対しては「不服申立て」が可能です。
ただし、調査期間が長引き、加算税率も高くなる傾向があります。(通常10%、重加算税は35%)
実務的には、調査官は手続きを簡略化するため、修正申告書の提出を強く勧めるケースが多いのが現実です。
税務調査と更正の請求の関係
更正の請求は、基本的に「税額を減らしたい」手続きですので、税務調査とは一見関係が薄いように思えます。しかし、実際には次のようなリスクが存在します。
請求をきっかけに調査が行われることがある
更正の請求書を提出すると、税務署は内容の正当性を確認するために、帳簿や領収書の提出を求めたり、実地調査を行ったりすることがあります。その過程で、他の部分に誤りが見つかると、逆に追加課税(修正申告の必要)が発生するケースもあります。
請求内容は明確かつ証拠を添付する
更正の請求を行う際は、単なる「思い込み」や「推測」ではなく、証拠書類を整えた上で慎重に行うことが重要です。誤った請求や説明不足は、かえって税務署の調査を招くリスクがあります。
まとめ:実務上のポイントと専門家活用
修正申告と更正の請求は、確定申告後の税額を是正するための重要な制度です。誤りに気づいた際は、それぞれの手続きの性質と実務上の注意点を理解し、特に修正申告は早めの自主的な対応を心がけることが、不必要なペナルティを避ける鍵となります。いずれの手続きも、税務調査のリスクや不服申立ての可否といった専門的な判断が必要となるため、迷った場合は必ず税理士などの専門家を活用した方が良いでしょう。税務調査の対応方針(修正するか、争うか)や、更正の請求の根拠資料の整え方によって、結果が変わってくることになります。
- ・修正申告は「税額が少なかった場合」、更正の請求は「税額が多かった場合」
- ・修正申告は「納税者の申告で確定」、更正の請求は「税務署の認定で確定」
- ・修正申告は早期に行えば加算税が軽減されるが、更正の請求は慎重に

監修者プロフィール
川口 誠(カワグチ マコト)
国税局では高度な調査力が必要とされる調査部において、10年以上にわたって上場企業や外国法人等の税務調査に従事する。また、国税庁においては、全国の国税局にある調査部の監理・監督を行い、国税組織の事務運営にも携わる。
略歴
平成24~28年 東京国税局 調査第四部各調査部門、調査第一部調査管理課
平成29~30年 国税庁 調査査察部 調査課
令和元~5年 東京国税局 調査第一部 国際調査課、国際調査管理課、広域情報管理課
令和6年 ON税理士法人と業務提携
実績
中小企業から上場企業等まで100以上の会社の税務調査を行う。
メディア・著書
「元国税の不動産専門税理士が教える!不動産投資 節税の教科書」
資格・免許
税理士
記事に関連する当事業内容
記事に関連する
当事業内容
CONTACT各種お問い合わせ
税務に関するあらゆる課題は
ON税理士法人に
お任せください
お電話でのお問い合わせ



