COLUMN
コラム
SCROLL
2025.04.24 税務コラム
法人の役員借入金に注意!債務免除益を避ける方法/税務コラム〜[vol.013]
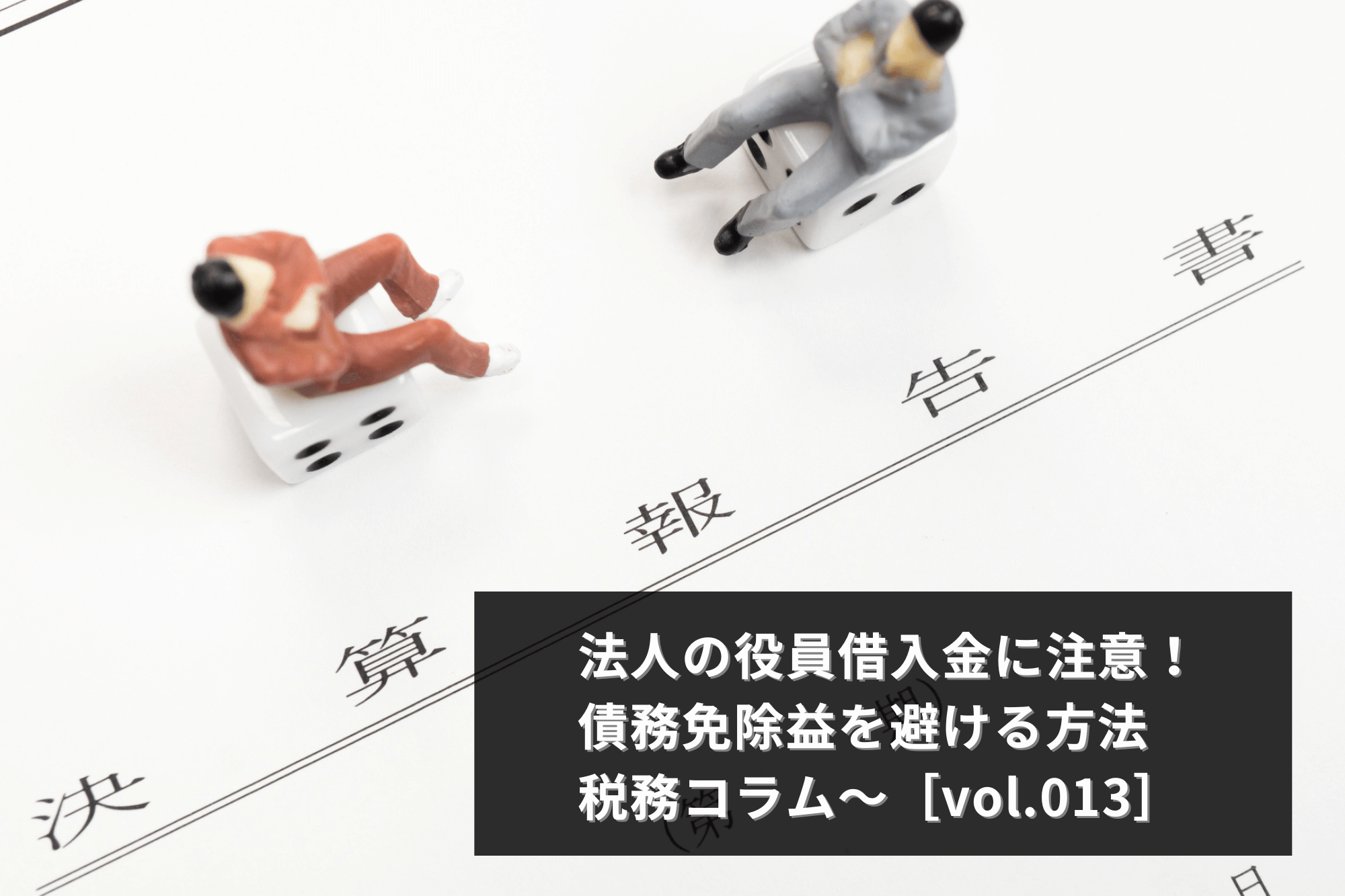
決算書に多額の役員借入金が計上されていませんか?役員借入金を債務免除することはできますが、法人税が課税される可能性がありますので、計画的に解消していく必要があります。
法人に多額の役員借入金が残っていると個人の相続財産になる
法人が役員借入金を保有しているということは、役員個人の立場から考えると、貸付金という資産があることになります。役員個人が亡くなった場合には、貸付金が個人の相続財産の対象となるということを意識しておかないといけません。
ただし、相続税法の基本通達205では、法人の破産や更生等によって貸付金の回収が不可能または著しく困難であると見込まれる場合には含めなくてよいということになっています。
しかしながら、法人の破産や更生等は稀なケースであり、相続を考えるとそれまでに役員借入金を解消しておきたいところです。
相続税法基本通達205(貸付金債権等の元本価額の範囲)
前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(平12課評2-4外・平28課評2-10外改正)
(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
ロ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があったとき
ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき
ホ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があったとき
ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2)更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3)当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
法人の役員借入金を解消する方法
役員借入金を債務免除し繰越欠損金と相殺
法人が役員借入金という債務を免除すると債務免除益が計上されます。その結果、利益が出ると法人税が課税されます。しかし、繰越欠損金が多く残っていたり、当期が赤字であったりすると、両者を相殺することができます。
ここで気を付けないといけないことは、役員借入金の対象となる役員と株主が異なる場合には、相続税法第9条と相続税法基本通達9-2により、役員から株主にみなし贈与が生じ、株主に贈与税が課税される可能性があるということです。何も贈与していないのになぜ贈与税が課税されるのと思われる方もいらっしゃると思います。それは、債務を免除し負債が減ることによって、その分の純資産の価額が増加し、株価が上がると考えるからです。目に見える贈与ではありませんが、実質的に贈与を受けたものとみなします。ただし、債務が免除された場合であっても、その後も負債が資産を超えるような債務超過の状態ですと贈与税は生じません。
相続税法第9条 第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるために なされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。 相続税法基本通達9-2(株式又は出資の価額が増加した場合) 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1、平20課資2-10改正) (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者 (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者 (3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者 (4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合 当該財産の譲渡をした者
現金預金で役員借入金を返済
一番良いのは、法人にキャッシュが潤沢にあるようでしたら、現金預金で役員借入金を返済することです。ただし、一括で多額に返済してしまうと一時的に資金が減り、その分をまた役員借入金に頼ってしまえば本末転倒です。資金繰りに余裕がある場合に行うことになります。
役員報酬の代わりに借入金を徐々に返済
役員報酬を支払っている場合には、資金があるということですので、代わりに借入金の返済に充てます。
役員個人の相続を見据えているのであれば、敢えて役員に報酬を支払い、資金を残す必要はありません。それよりも貸付金を解消し相続財産を減らすことによって、次世代の相続税負担を減らしていった方が良いかもしれません。
貸付金を後継者に贈与
役員個人の貸付金を後継者に贈与していくという方法もありますが、暦年贈与というかたちですので、毎年110万円と徐々に返済していくことになります。110万円を超えて一気に返済していくのであれば、贈与税と相続税との比較で、金額を決めていく必要があります。
DESや疑似DESを使って資本にシフト
DES(デット・エクイティ・スワップ)や疑似DESによって役員借入金という負債を資本に振り替える方法があります。DESでは、役員借入金をDCF法等により時価で評価することになり、時価との差額が債務消滅益として法人税がかかることになります。疑似DESでは、役員借入金を返済した上で、その資金を法人に出資する流れになります。
DESや疑似DESを行うと資本金が増え、地方税の均等割額の負担が増えることになります。また、上記の債務免除益の説明の際に記載した通り、純資産の金額に影響しますので、みなし贈与の問題についても考慮する必要があります。
DESや疑似DESは、通常、企業再生等で行われることになります。検討すべき事項が多いですし、同族会社の行為計算否認等の税務上のリスクもありますので、この方法を採用される場合には、税理士等の専門家に相談してから行うようにしてください。
役員借入金に頼らずに経営や経理処理を行う
創業時は、資本金だけでなく、代表者等の役員借入金を原資として事業をスタートさせることも多いと思います。将来的には、法人の事業から得られる資金で役員借入金を返済するとともに、役員借入金に頼らずに会社を経営していくことが大切です。
中小企業では一時的に役員が経費等を立て替えて支払う場合には、相手勘定科目を役員借入金として処理することが多いかもしれません。したがって、普段から役員借入金ではなく、立替金、仮払金等の勘定科目を使って経費精算を行う経理処理も大切になってきます。塵も積もれば山となり、役員借入金の金額が多くなることもあります。

監修者プロフィール
川口 誠(カワグチ マコト)
国税局では高度な調査力が必要とされる調査部において、10年以上にわたって上場企業や外国法人等の税務調査に従事する。また、国税庁においては、全国の国税局にある調査部の監理・監督を行い、国税組織の事務運営にも携わる。
略歴
平成24~28年 東京国税局 調査第四部各調査部門、調査第一部調査管理課
平成29~30年 国税庁 調査査察部 調査課
令和元~5年 東京国税局 調査第一部 国際調査課、国際調査管理課、広域情報管理課
令和6年 ON税理士法人と業務提携
実績
中小企業から上場企業等まで100以上の会社の税務調査を行う。
メディア・著書
「元国税の不動産専門税理士が教える!不動産投資 節税の教科書」
資格・免許
税理士
記事に関連する当事業内容
記事に関連する
当事業内容
CONTACT各種お問い合わせ
税務に関するあらゆる課題は
ON税理士法人に
お任せください
お電話でのお問い合わせ



